契約とは?

契約とは、一般的に「法的効果を生じさせる約束」と解釈されます。当該契約は、当事者間の意思表示の合致によって成立し(民法522条1項)、権利と義務が発生します。契約が締結されると、当事者はその内容に拘束され、契約内容を遵守しなければなりません。
相手方が約束を違反した際には、契約違反として、履行の追完、損害賠償の請求、あるいは契約の解除が可能です(民法第414条、第415条、第541条、第542条)。さらに、債務不履行が発生した場合、訴訟を通じて判決を勝ち取り、強制執行を行うことも可能となります(民法第414条1項)。
- 契約は「法的効果を生じさせる約束」。
- 契約は当事者間の意思表示の合致で成立。
- 契約成立により権利と義務が発生。
- 当事者は契約内容に拘束され、遵守が必要。
- 約束の違反があった場合、履行の追完、損害賠償の請求、または契約の解除が可能。
- 義務不履行があった場合、訴訟を通じて判決を得て、強制執行が可能。
契約自由の原則
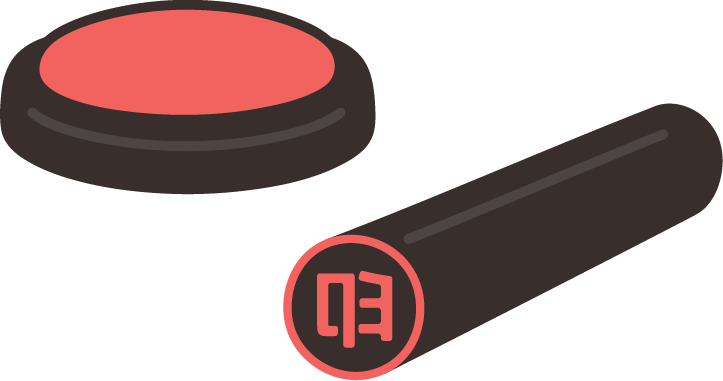
民法では、「契約自由の原則」が規定されており、これにより、契約当事者は「契約を結ぶかどうか」、「誰と」、「どのような内容で」、「どのような形態で」契約を結ぶかを自由に決定できます。
この「契約自由の原則」は、以下の4つの要素から構成されています。
- 締結の自由
- 相手方選択の自由
- 内容の自由
- 方式の自由
締結の自由
締結の自由は、ある法律により契約することが義務付けられていない限り、契約するかしないかは自身で自由に決定できるという理論をいいます。民法第521条第1項にて以下のように定められています。
何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
内容の自由
内容の自由とは、法律に反しない限り、自身で自由に契約内容を決定できるという理論です。
民法521条第2項にて以下のように定められています。
契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。
相手方選択の自由
相手方選択の自由とは、公序良俗に反しない範囲で、自身で自由に契約の相手方を選択できるという理論です。
方式の自由
方式の自由とは、法律に特別の定めがある場合を除き、どういう方法で契約を締結するかを自身で自由に決定できる理論です。
民法第522条第2項にて以下のように定められています。
契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
- 締結の自由:契約当事者は「契約を締結するか否か」を自由に判断可能。
- 相手方選択の自由:「誰と」契約を締結するか契約当事者が自由に選定可能。
- 内容決定の自由:契約当事者は「どのような内容で」契約を締結するかを自由に決定可能。
- 方式の自由:「どのような形(方式)で」契約を締結するかを自由に決定可能。
契約の成立条件

意思の合致の到達
契約は、当事者の一方(以下、「申込者」という。)が契約の内容を明示的又は黙示的に示して申込みをし、相手方による当該申込みに対する承諾の意思表示が、申込者に到達した時点で成立します(到達主義)。
契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
契約の形式
契約の成立には必ず書面が必要というわけではありません。口頭による約束でも契約は成立するためご注意ください(方式の自由)。
契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
- 一方の当事者(申込者)が契約内容を明示的または黙示的に示し、相手方が承諾の意思表示をし、これが申込者に到達した時に契約は成立する。
- 方式自由:契約の成立には必ずしも書面は必要ではない。口頭による約束でも契約は成立可能。
申込みとは

概要
申込みとは、申込者が特定の契約を成立させようとして、相手方の承諾を求める意思表示をいいます。
申込みの種類
申込みには2種類あります。
一般の申込み(売主→買主)
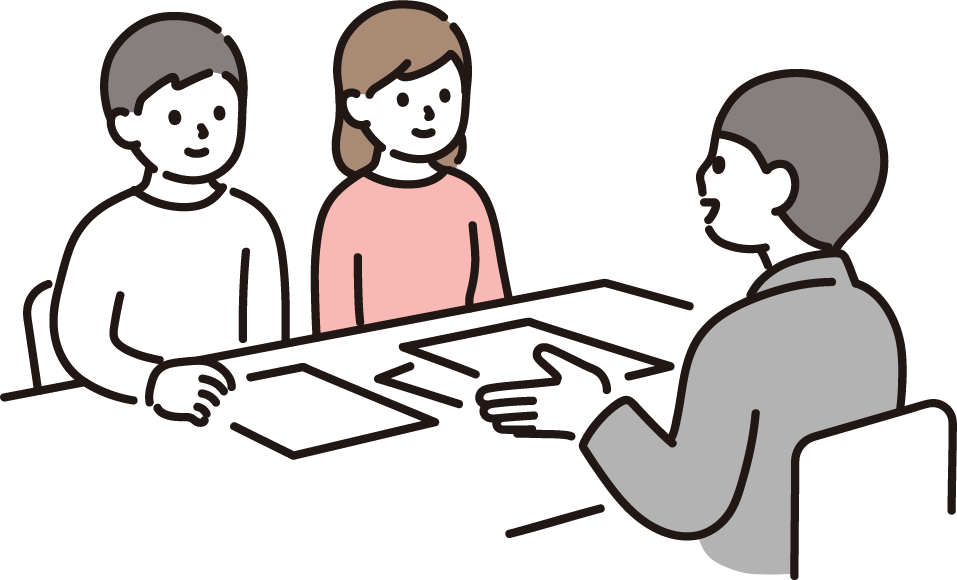
1つは、『当事者の一方が「特定の人物に対し契約締結の提案」をすること』です。
不動産売買で例えると、セールスマンが通りすがりの人物に対して「この家を買いませんか?」と提案することです。
売主が買主に対して申込みをしています。
「申込みの誘因」を経由した申込み
(誘引→買主→売主)

もう一方は、『Aがチラシ又は広告等に商品又はサービスを掲載し、Bが「この商品又はサービスいいな」と考え、Aに対して「契約締結の提案」をすること』です。
不動産売買で例えると、『不動産会社がチラシを消費者へ頒布し、当該チラシを見た購入希望者が不動産会社へ購入の意思表示をすること』です。
当該チラシの頒布は、申込みしませんか?というお誘いであり、法律用語としての『申込みの誘因』と言われています。
こちらは、買主が売主に対して申込みをしています。
2つの差異は、申込者が売主か買主かです。
どちらにしても申込みは必須ですが、上記の仕組みを理解することで、契約成立の有無について揉めた際にスムーズに解決することができます。
実際にあったケース

例えば、『ネット販売でAが掲載している商品についてBは購入した。BにはAからの受注を確認した旨のメールが送信されていない。』というケースにおいて、こちらは契約が締結されていると思いますか?
答えはNOです。
『ネット販売でAが掲載している』という行為は『申込みの誘因』に該当し、申込みではありません。
そのため、『ネット販売でAが掲載している商品についてBは購入した。』という行為は『申込みの誘因に対する申込み』ということになります。
そして『BにはAからの受注を確認した旨のメールが送信されていない』という部分からBは申込みについて承諾をしていないということが分かります。
そのため、Bは民法第522条第1項に規定されている契約締結に必要な『申込みへの承諾』をしていないため契約は締結されていません。
余談ですが、特殊なケースで両当事者が同時に申込みをするというケースがあります。このことを『交叉申込み』といいます。この場合は、後の申込みが相手方に到達した時に契約が成立することになると解されます。
- 申込み:
特定の契約を成立させようと、相手方の承諾を求める意思表示。 - 申込みのタイプ:
- 売主から買主への申込み(例:不動産のセールスマンの提案)。
- 買主から売主への申込み(例:チラシや広告を見ての提案)。このタイプは「申込みの誘因」とも言われる。
- 差異:
申込者が売主か買主か。 - 契約未成立の例:
ネット販売において、商品の掲載は「申込みの誘因」であり、購入者からの受注確認メールがない場合は、契約は成立していない。 - 交叉申込み:
両当事者が同時に申込みをするケース。後の申込みが相手方に到達した時に契約が成立。
申込みは撤回できる?

申込みの効力
申込みを受けた相手方は、当該申込みを承諾すべきか検討し、そのために調査等の準備をします。
そこで申込者が一方的に当該申込みを撤回しては、申込みを受けた相手方に迷惑がかかってしまいます。
そのため、申込みには『申込みの撤回は一定の場合にしか申込みを撤回することを認めない』という効力が認められています。
これを『申込みの拘束力』といいます。
撤回できるケース

では、どのような場合に申込みを撤回できるのでしょうか。
- 承諾の期間を定めてした申込み
- 承諾の期間を定めないでした申込み
上記2つのケースで撤回できる場合は異なりますのでご注意ください。
承諾の期間を定めてした申込み
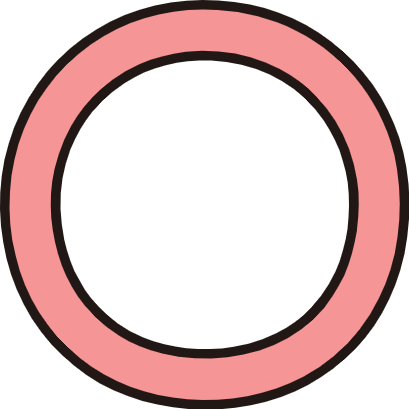
民法には以下の規定があります。
承諾の期間を定めてした申込みは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
承諾の期間を定めでした申込みとは、『AがBに対して今月末までに承諾するか否かの連絡を下さい』という申込みをいいます。
この場合は、承諾の期間を定めた申込みとして、原則撤回することができません。
しかし、例外として同条後文にある『撤回権の留保』をしていれば撤回することができます。
『撤回権の留保』の具体例としては、通信販売への申込文の中に『ただし、売主の仕入先が倒産等、不可抗力により履行できなくなった場合はこの限りではない』と付すことが挙げられます。
承諾の期間を定めないでした申込み

民法には以下の規定があります。
承諾の期間を定めないでした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
第525条第2項
対話者に対してした前項の申込みは、同項の規定にかかわらず、その対話が継続している間は、いつでも撤回することができる。
第525条第3項
対話者に対してした第一項の申込みに対して対話が継続している間に申込者が承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。ただし、申込者が対話の終了後もその申込みが効力を失わない旨を表示したときは、この限りでない。
第1項の規定は、『承諾の期間を定めてした申込み』と類似しています。
撤回の可否について『承諾の期間を定めてした申込み』では『定めた期間内は撤回することができない』という規定でしたが、『承諾の期間を定めないでした申込み』では『申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは撤回できない』という規定になります。
しかし、『承諾の期間を定めてした申込み』の場合は、対話(契約交渉)が継続している限り、申込者はいつでも撤回することができます(民法第525条第2項)。
なお、対話(契約交渉)が終了した場合でも、申込者が『対話(契約交渉)の終了後も当該申込みが効力を失わない旨を表示していた時』は撤回することができないためご注意ください。
・承諾の期間を定めた申込み
- 原則として撤回不可
- 民法第523条第1項に基づき、承諾の期間を定めてした申込みは原則として撤回することができない。
- 撤回権の留保
- 申込者が撤回権を留保した場合、例外として申込みの撤回が可能。
- 例:仕入先が倒産等、不可抗力により履行できなくなった場合。
・承諾の期間を定めない申込み
- 相当な期間
- 民法第525条第1項に基づき、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、原則として撤回することができない。
- 対話中の撤回
- 対話(契約交渉)が継続している間は、いつでも撤回することができる(民法第525条第2項)。
- 対話後の撤回
- 対話が終了した後も、申込みが効力を失わない旨を申込者が表示した場合、撤回はできない(民法第525条第3項)。
これらの点を踏まえ、申込みをする際や申込みを受けた際は、撤回の可否に注意する必要があります。
契約の有効条件5つ
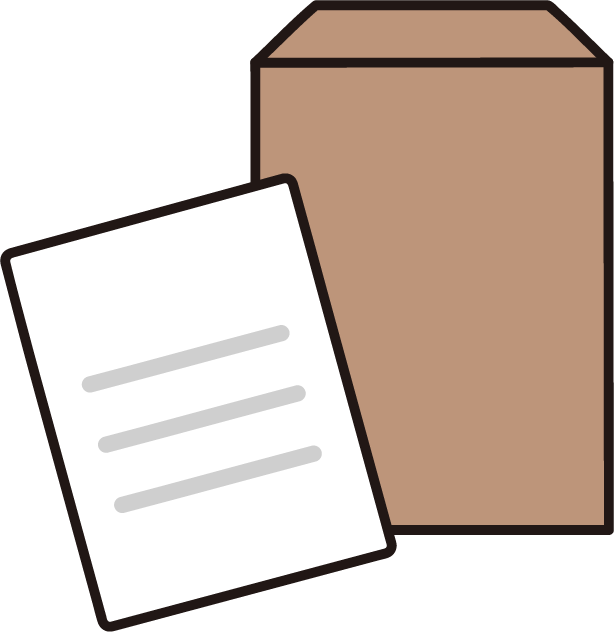
契約が成立したとしても、有効でなければ効力はなく、すなわち無効となります。
ではどういう場合に有効となるのでしょうか。
有効となるには以下の5つの要素を全て満たす必要があります。
契約内容が
- 公序良俗に反しない(社会的妥当性)
- 権利義務の内容が明確であること(確定性)
- 強行法規に反しない(適法性)
契約当事者が
- 意思能力を具備していること
- 意思表示が虚偽又は真意でないこと
公序良俗に反しない(社会的妥当性)
公序良俗については以下のように規定されています。
公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
『公の秩序』とは、国家および社会の一般的利益を、『善良の風俗』とは、社会の一般的倫理を意味します。
権利義務の内容が明確(確定性)
契約が成立すると、各当事者に法律的な権利と義務が発生します。
ただし、契約内容が曖昧である場合、各当事者の権利や義務もまた不明確となり得ます。
例えば、商品の購入に際し、商品の価格が明確でなければ、困惑するでしょう。
従って、契約の内容は、全ての当事者にとって明瞭かつ理解しやすいものでなければなりません。この理論が契約の『確定性』の本質です。
強行法規に反しない(適法性)
契約が無効にならないようにするためには適法性を遵守する必要があります。
適法性とは、強行法規に反しないことです。
例えば、『債務者の過失により債権者に損害が生じた場合でも、債務者は損害賠償義務を負わない』という規定が契約内容にあった場合、この条項は無効となります。注意すべき点は契約全体が無効となるのではなく、条項単位で無効となります。
強行法規は、債権者又は債務者を保護する必要が特にある場面で用いられるため、内容の自由が及びません。
なお、実務においては消費者契約法に違反したことにより無効となるケースがあります。
そのため、取引の規制対象となる法律をよく確認する必要があります。
意思能力を具備していること

契約が無効にならないようにするためには適法性を遵守する必要があります。
適法性とは、強行法規に反しないことです。
例えば、『債務者の過失により債権者に損害が生じた場合でも、債務者は損害賠償義務を負わない』という規定が契約内容にあった場合、この条項は無効となります。
注意すべき点は契約全体が無効となるのではなく、条項単位で無効となります。
強行法規は、債権者又は債務者を保護する必要が特にある場面で用いられるため、内容の自由が及びません。
なお、実務においては消費者契約法に違反したことにより無効となるケースがあります。
そのため、取引の規制対象となる法律をよく確認する必要があります。
意思能力とは、契約締結当時に自分の行為(契約)がどのような法的効果を発生させるのかを認識し得る精神的能力をいいます。
契約は意思表示の合致(合意)であり、法律効果の発生を求める当事者の意思が基礎となっています。
その基礎となる意思がなければ当然、契約の効力は認められません。
例えば、精神障害により正常な判断を全くできなくなった者が形式的に契約書に署名押印をして契約を成立させても、その契約は無効となります。意思能力の有無はその法律行為の性質に照らして判断されることになります。
判例では7歳3ヶ月の者でも贈与を受けて不動産を取得するという意思決定はできるとしたものがあり(大判昭和5年10月2日民集9巻930頁)、また、13歳5ヶ月の者は不動産売買をする意思能力があるとされた(大判昭和15年7月31日評論29巻民法700頁)例もあります。
意思表示が虚偽又は真意でないこと

虚偽の意思表示
契約の相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効となります。民法第94条第1項にて下記のように規定されています。
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
例えば、債権者からの強制執行を免れるために、AがBと通謀して、本当は不動産を売る気がないのに、売ったように見せる行為をしたとしましょう。
通謀とは、AとBの両方に上記のような悪さをする意思があることです。
そのため、仮にBがAが上記のような悪さをすることを知らず、正当な目的で不動産を購入した場合(善意の場合)はAにどんな思惑があろうと有効に成立します。
※有効に成立したとしても後述の『契約取消し』をされる場合があります。そのため債権者が目的物を処分する権利を正当に所有しているかよく確認しましょう。
真意でない意思表示
真意でない意思表示(心裡留保)は、民法第93条第1項により無効となることが規定されています。
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
当規定は、真意でない意思表示をされた相手方を保護するために制定されました。例えば、AがBに冗談で自分の不動産をタダであげるという意思表示をしたとしましょう。
この場合は、Bは通常、Aの真意(冗談であること)を知らないのですから、ここで『実は冗談だったんだ。』と言われ契約を反故にされると、Bはとても困ります。そのため契約は有効に成立します。
一方、BがAの真意(冗談であること)を知っていた(悪意であった)場合又は注意すれば知ることができた(有過失であった)場合はBを保護するに値しないため、無効となります。
契約が有効となるためには、以下の5つの要素を全て満たす必要があります。
- 契約内容が公序良俗に反しない(社会的妥当性)
- 民法第90条に基づき、公の秩序や善良の風俗に反する法律行為は無効。
- 権利義務の内容が明確であること(確定性)
- 契約内容は全ての当事者にとって明瞭かつ理解しやすい必要があります。
- 強行法規に反しない(適法性)
- 契約内容が強行法規に反する場合、該当条項は無効。
- 実務においては消費者契約法に違反したことにより無効となるケースがある。
- 契約当事者が意思能力を具備していること
- 契約締結当時に法的効果を認識し得る精神的能力が必要。
- 意思能力の有無は法律行為の性質に照らして判断される。
- 意思表示が虚偽又は真意でないこと
- 民法第94条第1項に基づき、相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効。
- 民法第93条第1項に基づき、真意でない意思表示も無効となる可能性がある。
これらの要素が満たされない場合、契約は無効となり、法律効果は発生しません。




